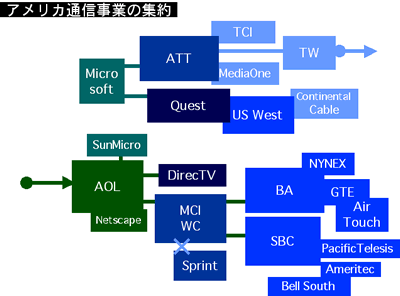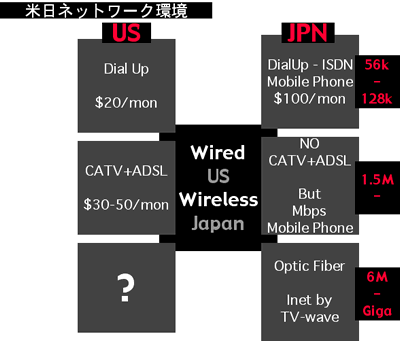|
8.2�@�d�q������̌���
8.2.1�@B to C�T��
�@�A�����J�̓d�q������̏����s��͓��{��10�{���炢����Ƃ����B���̎s��K�͂Ɋւ��Ă͂��܂�ɑ��l�Ȑ��������\����Ă���A���ꂼ���`��v���͈͂��قȂ�i�Ⴆ�A�l�b�g�Ŕ������k������Ŗʒk�ōw�������s���Y�̉��i��d�q������ɉ����邩�ۂ��j�̂ŁA���l��p����̂͊댯�Ȃ̂����A�K�͂̍����傫�����Ƃ͎����ł���B
�@����99�N�V���A�o�c�A�͒̒��ŁA�A�����J�œd�q����������B�������R�Ƃ��āA
�@�m��\�����p�\�R���Ōl���s���Ă�������
�A�ʐM�̔��̓y�낪����������
�B�x���`���[�L���s�^�������邩��
���̎������w�E�����B
�@���̈Ӗ��ł́A�A�����J����s����͓̂��R���B�ʔ̎s�ꂪ60�{�̋K�͊i���ł���Ƃ��A���{�ł̓R���r�j�����y���Ă��Ė邠�邢�Ă����S�ł���Ƃ��A�މ�̏����Ă���ƁA�t�ɓ��{�̂ato�b�͌��\�����������Ă��Ă���ƕ]���ł���B
99�N�̃N���X�}�X����ł̏����́A�S�Ă�60���h�����x���Ƃ����B98�N�P�N�Ԃ�70���h������ 150���h���ƌ����A������N���X�}�X���Ԃ����ŃJ�o�[����قǓd�q��������������x���ɂ܂ŐZ�����Ă��Ă���B
�@99�N�̃N���X�}�X����ł�60���h���̂����A���i�i���Ђ₨������A���y�̂b�c���j��50���h�����炢�ŁA���s��10���h�����炢���Ƃ����B�܂��A�`�n�k������25���h�����҂����Ƃ����B
�@�������A2000�N�V���ɑS�ď����Ƌ�����\�����Ƃ���ɂ��A99�N�̑S�ď����Ƃ̔���͖�R���h���ŁA����ɐ�߂�l�b�g����̔䗦�͂P�`�Q�����Ƃ����B�Ƃ���A�c��99�����s��Ƃ��čL�����Ă���킯�ł���A����̐����ɂȂ����҂��W�܂�̂����Ȃ�����B
8.2.2�@�͂�����
�@B to C���肪�����Ƃ́A�ڋq�̈͂����݂��ő�̊�ڂƂ��Ă���B�����ҁE���p�Ґ��𑝂₷���ƁA�����ăE�F�u�̑؍ݎ��Ԃ�N���b�N���𑝂₷���ƁA�Ɍ������헪������Ă��Ă���B
�@�č��ݏZ�̃W���[�i���X�g�ł��鏬�r�ǎ����̓��@�ihttp://www.ryojikoike.com�j�ɉ����Ă��̗�����ς�ƁA�����ނˈȉ��̂悤�ȏ��ɃT�C�g�Q�������オ���Ă��Ă���B
�@�����T�[�r�X
�T�[�`�G���W���ɂ��q����
�A�J�X�^�}�C�Y
�j���[�X��V�C�\����l�ʂɃj�[�Y������ő��M
�B�����T�[�r�X
�^�_�̃��[���A�^�_�̃z�[���y�[�W�쐬�Ȃ�
�C�R�~���j�e�B��
�`���b�g�A�t�H�[�����Ȃ�
�D�V���b�s���O���[��
�������[��(AOL)�A�t���[�}�[�P�b�g�i���t�[�j�A�X�[�p�[�}�[�P�b�g�i�A�}�]���j
�E�I�[�N�V����
�F�e�[�}�|�[�^��
�@���������A�q�������A����Ҍ����A�X�|�[�c�A���y�A���Z�A�����ԁA�Ɠd�@�Ȃ�
8.2.3�@�u�����h���
�@ �ŋ߂̓����Ƃ��āA�e���r�̃R�}�[�V�����Ƀh�b�g�R���n�������Ă��邱�Ƃ���������B�e���rCM���t�q�k�A�Č^�ɐ������ꂽ����������B99�N1���A�A���t�g�̃X�[�p�[�{�[���ł́A30�b�̍L���g��200-300���h���Ŕ����Ă����Ƃ����B���̂b�l�ɂ͕��������Ƃ��Ȃ��h�b�g�R���n��Ƃ��W�����A�O�N�̔���̔���������CM�P��ɒ�����������Ƃ�����Ƃ����B
�@�ڋq���l�����邽�߂̔F�m�x���グ��̂ɑS�͓��������Ă���p�ł���A�u�����h���m���������Ƃ����ߓn���̎p���낤�B�������A����Ȃɑ����̐V���u�����h���ł���킯�͂Ȃ��A�t�ɍ��u�����h�������Ă��閼���Ƃ��h�b�g�R���n�Ɠ��l�̃C���^�[�l�b�g�Ή������Ă����珟�s�̗\���͂��₷���B
�@�l�b�g�n�A�h�b�g�R���n�͖{���A�q���c�^�̓����Ńr�W�l�X���f�����X�V����Ƃ���ɐ����̖{��������B�s��J��̂��߂Ƀe���r�b�l�Ƃ����c�Ƃ�}�[�P�e�B���O�Ɏ����𓊓�����X���́A���n�ł͂Ȃ������̑O���ł͂Ȃ����B���̌X���͒������͂��Ȃ����낤�B
�@���Ȃ݂Ƀe���r�ƃC���^�[�l�b�g�̊W�Ō����A�ŋ߁A�C���^�[�l�b�g�𗘗p���Ȃ��瓯���Ƀe���r���������郆�[�U���������Ă���Ƃ����B������Ѓf�[�^�N�G�X�g�ɂ��A�e���r�����Ȃ���o�b�ŃC���^�[�l�b�g�𗘗p����l�i�e���E�F�o�[�Y�ƌĂ��j���A98�N��800���l����99�N��2700���l�ɋ}�������Ƃ����B�j���[�X�����Ă���ۂɃC���^�[�l�b�g�ŏڍ���A�X�|�[�c�ϐ풆�Ɋ֘A����A�Ƃ������g���������Ă���炵���B
�@����A�o�b��ʂŃe���r������Ƃ����^�C�v�̓R���s���[�^�ƊE�̖ژ_���ɔ����ĐL�єY��ł���炵���i99�N��210���l�j�B�p�\�R���ƃe���r�͌����ڂ�@�\�����Ă����ɂ�������炸�A���炭�ʁX�̃n�R�Ƃ��đ��݂��Ă�������̂悤���B
�@B to C�ł́A��l�̌ڋq���l�����邽�߂�100�h���ȏ�̃R�X�g�������邱�Ƃ���ԂƂȂ��Ă���B�������ŋ߁A�h�b�g�R���Ԃł̒�g��ʂ��A����T�C�g�Ŕ�����������Ƒ��T�C�g�ł��g����N�[�|�������炦��Ƃ������݃��x�[�g�����铮���Ȃǂ�����A�ڋq�l���̂��߂̎�@�ɂ������^�̍L���肪������悤�ɂȂ��Ă���B
8.2.4�@B to B�̗���
�@B to B��B to C��10�{�̋K�͂Ői�W���Ă���Ƃ����B�d�q������̃r�W�l�X�Ƃ��ẮA�ŏI�����������B to C�����A���Ԑ��Y���𗬒ʂ�����B
to B�̕����͂邩�ɑ傫�Ȏs��ƂȂ��Ă���B
�@�����10�N20�N�ȑO����n���ɐi�߂��Ă�����Ƃ̃l�b�g���[�N�����C���^�[�l�b�g�̐i�W�ɂ���čL�����y���͂��߂����̂��B���A���B�A�����Ǘ��A�ɊǗ��A�����Ǘ��Ƃ�������Ɠ��E��ƊԂ̋Ɩ����I�����C���ōs���邱�Ƃ��A����悤�₭�{�i���������̂ł���B
�@���ɁA���ޒ��B���l�b�g�ōs�����Ƃ�B to B�̒��Ƃ��čL�����Ă���B���Ƃ��A�����Ԑ�����H�i�Ȃǂ̕���ŁA�����葤�̓��Ǝ҂��A�g���Ē��B�̎s����T�C�g��ɐݒ肵�A�R�X�g�_�E���ƌ�������}��Ƃ�����@�ł���B�܂��A�]���̉����Ǝ҂����̋ƊE�̒��B���d��`�ŏ��o���Ă������݂���B���i�A���Օi�Ȃǂ������Ă��邾���łȂ��A�d�͂�K�X�A�ʐM����Ȃǂ��ƊE���̃u���[�J�[�I�ɂ����悤�ȃr�W�l�X������B
�@����͈��̎���s��ł���B�R�~���j�e�B���`�Â��邱�Ǝ��̂��r�W�l�X�Ƃ��Ă���_�́A�l�b�g�̖{���I�ȓ����������������̂Ƃ��Ē��ڂ��ׂ��ł��낤�B
8.2.5�@�R�~���j�e�B�Ƃ��Ă�C to C
�@�������������ɎQ�����邽�߁AERP�ƌĂ��p�b�P�[�W�\�t�g�𗘗p�����Ƃ��������Ă���B�����I�ȋƖ��p�\�t�g���J�X�^�}�C�Y���ē������A�S�Ђ̃l�b�g�Ή���}�낤�Ƃ�����̂��B�����A�I�����C���ŋƖ������Ȃ����Ǝ҂����X�Ɠo�ꂵ�Ă���B�����畨���A�����A����ɂ͉c�Ƃ�L���A�ڋq�Ǘ��ȂNJe��Ɩ��������O���ɈςˁA���Ђ͒��j�I�ȓ��ӗ̈�ɓ�������Ƃ����헪�����藧�B�܂��ɑ����̘A�g��O��Ƃ���l�b�g�I�ȃr�W�l�X��@�ł���B
�@���̉����ŁA��ƊԂ����łȂ��A�ڋq���܂߂��L��̂悤�ȃT�C�g�������������Ă���B�bto�b�Ƃ������ׂ��������B�I�[�N�V������ebay�����������A�Q����̂���Ƃł��邩����҂ł��邩�Ƃ�����ʂ͂��͂�{���ł͂Ȃ��A���⏤�i�̔����E�������s���R�~���j�e�B�̃v���b�g�t�H�[���Ƃ��ăl�b�g�Ȃ�ł͂̋@�\����������Ă���B
�@���̃r�W�l�X�̓��f���Ƃ��Ċm��͂��Ă��Ȃ����A���[�U���m������������Ƃ��̃g�����U�N�V�����ɉۋ�������@�A�V���o����悱���Ƃ����ꏊ�݂��^�C�v�A�����Ă����̃~�b�N�X�Ƃ�������@���݂��A���̃|�[�g�t�H���I��T���Ă���ɂ���B
�@99�N11���̐����ł́Aebay�͂P���� 145��7000�g�����U�N�V����������Ƃ����B�A�}�]���E�h�b�g�R����81.5�����A�o�[���Y�A���h�m�[�u����32.8�����Ƃ�������A���Δ������K�͂��B���̑�C
to C�n�ł́A���Ƃ��ΓS�|���i�A�s���Y�A�q�A��c��̗Z�ʁA�Y�Ƌ@�B�A�p�\�R���ȂǁA�e��̃R�~���j�e�B������B
�@�u�����h���͌ڋq���𑝂₷���@�����A����ɁA����烆�[�U�������ɐ[�������ԃT�C�g�ɗ��܂点�邩���d�������X���ɂ���A���̎�@�Ƃ��ẴR�~���j�e�B��ԂÂ��肪���ڂ���Ă���B�s������Ƃ����r�W�l�X�͍�����������邱�Ƃ������܂��B
8.2.6�@�A�h�o�C�U�[�Ɨ��p�҃p���[
�@�ڋq������������A�����ԃT�C�g�ɑ؍݂������肷��Ɠ����ɁA�ڋq�Ƃ̊W�����[�����邽�߂̎�@�����߂��Ă���B�T�[�r�X���J�X�^�}�C�Y���A�l�����ɂ����ߏ��i�Ȃǂ̏����E�F�u���[���Œ�����̂������Ȃ��Ă���B
�@�R���s���[�^��Ɠd�A�ԂȂǂ̔̔��ł́A���R�~���j�P�[�V������[�߂āA�T�C�g��ő��k��i�߂Ȃ��珤�i�̑I����i�߂Ă����T�[�r�X���o�ꂵ�Ă���B���������T�[�r�X��@�\�̓A�h�o�C�U�[�ƌĂ�Ă���B
�@�t�F�f�b�N�X�̂悤�ɁA�ڋq�������̒������g���b�L���O�ł���悤�ɂ��Ă���Ƃ��������B����͎��Ѓf�[�^�x�[�X�̃V�X�e�����ڋq�����p���邱�Ƃ��\�ɂ��Ă�����̂��B
�@�l�b�g���[�N�́A���i�E�T�[�r�X�����痘�p�ґ��ɏ�������i�Ƃ��Ă����łȂ��A�҂Ɨ��p�҂��Θb����o�����̋@�\���d�������悤�ɂȂ��Ă��Ă���B�q�̔��Ȃǂł́A���p�҂��҂ɉ��i���̏�������͂��A�ґ�����D�����������o���i�܂�l��j�T�[�r�X��������B���i�����������痘�p���Ƀp���[�V�t�g���Ă���킯���B
�@�Ȃ��A�l�b�g��ł̏��i�E�T�[�r�X�́A�c�Ƃ◬�ʁE�ɊǗ����ɗv����R�X�g���啝�ɍ팸�����ƂƂ��ɁA���̓X�܂⎖�Ǝ҂Ƃ̔�r���u���ɍs���邽�߁A���i�E�����ɂ͏�ɒቺ�h���C�u��������B
�@MIT�X���[���X�N�[����Brynjolfsson�����ɂ��A���ۂ̓X�܂ł̔̔��ƃl�b�g�̔��Ƃ��r���������A�{�̉��i��9-16�������A���yCD��9-13�������ݒ肳��Ă���Ƃ����B������Ƃ����ė��_�I�Ɉꕨ�ꉿ���������邩�Ƃ����ƁA�����������Ƃł͂Ȃ��炵���A�l�b�g�̔��ɂ����Ă����i�̂���͎c�����܂܂ŁA�T�[�r�X�i����u�����h�Ƃ������̂̓l�b�g��ł��Ȃ��͂�����������悤�ł���B
8.2.7�@�A�O���Q�C�^�[�ƃG�[�W�F���g
�@�e��̃T�C�g���m���r����T�C�g������B���Ƃ��Ζ{�̃^�C�g������͂���ƁA���̉��i�������@�Ȃǂ̃f�[�^���֘A�T�C�g����W�߂Ă��āA��r���Ē���T�[�r�X���B�������������W�E���́E�T�[�r�X��\�t�g�̓A�O���Q�C�^�[�ƌĂ�A���Ђ̂ق��A�Ɠd�A�q�A���Z���i�Ȃǂ��܂��܂ȃW�������̂��̂��o�ꂵ�Ă���B
�@�������W�����͂��鑤�ɗ����Ăǂ��r�W�l�X�Ɋ������̂��B���ꎩ�̂��ڋq�T�[�r�X�Ƃ�����@�����낤�B�܂��A���Ƒ��Ђ̏��i�E�T�[�r�X�Ǝ��Ђ̂��̂Ƃ��r���A�ڋq�ɂƂ��čł��L���ȁi���ЂɂƂ��ĕs���ȁj�����ɍ��킹�Ē��邱�Ƃɂ���Ĕ�����m�ۂ���Ƃ�����p�����낤�B���̃r�W�l�X���f���̍\�z���܂��͍��i�K�ɂ���B
�@����A�����W�߂��鑤�ɂƂ��ẮA�ǂ̂悤�Ɏ��Ђ̏�W�߂��A���͂���A����邩�͎������ƂȂ�B��r�����Ƃ����O��ŏ��i�E�T�[�r�X�̐v����̕\�����@�Ȃǂ����肵�Ă����K�v������B���Ђ̏����W�߂��邱�Ƃɕs��������Ƃ��A�O���Q�C�^�[�����i�������A�A�O���Q�C�^�[�����̉�Ђ̏����r�Ώۂɂ��Ȃ��Ȃ������Ƃ̉e�����傫�����ƂɋC�Â��A�����H���ɔ��]�����Ƃ����������Ƃ����B
�@���������T�[�r�X�̐S�����ɂ���̂��G�[�W�F���g�Z�p�ł���B�T�C�g���߂����ď������W���Ă���͈̂��̃G�[�W�F���g�\�t�g���B�ڋq�̓|�[�^���T�C�g�œX�ƒ��ڂɌ����邾���ł͂Ȃ��B����葤�̃G�[�W�F���g�ɑ��A�ڋq�̔�����G�[�W�F���g�������Ęb���܂Ƃ߂�Ƃ����s��������������B
�@�G�[�W�F���g�͋Z�p�J�������߂��Ă����ƂƂ��ɁA�����┻�f�����ǂ��܂Ŏ�������̂��Ƃ�������p�_�������A����̃C���^�[�l�b�g�̃A�v���P�[�V�����ɂ����Ē��S�I�ȋc�_�ΏۂƂȂ낤�B���N��ɂ̓G�[�W�F���g�Z�p����g�����V�����T�[�r�X�������o�ꂵ�Ă���Ɨ\�������B�l���[�U�ł��A�����������łȂ��A�l�b�g��ł̑����̊������G�[�W�F���g�ɑ�s�����Ă����A�Q�Ă���Ԃɂ����Ȏd�������������Ă����Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ������̂��̂ƂȂ낤�B
8.2.8�@�o�[�`�����ƃ��A��
�@�A�����J�̓d�q������͋}���ɐi�݁A����ȋ������s���Ă���B���ɃI���`���A�m���A�r�f�I�̔̔��ȂLjꕔ�̃h�b�g�R������ɂ͓����̓�����������B�������A�{���ɓd�q��������{�i������̂͂��ꂩ�炾�B
�@����܂ł̃h�b�g�R���n�́A���̑��������q�l�ɑ��Ă̑������J�����Ƃ������Ƃł���A�����̏�̒i�K���B��Ǝ���̎�t��������Ƃ������������E�F�u�T�C�g���s����悤�ɂ����ɉ߂����A���̃o�b�N�ɂ���ɊǗ��A�����A�����E�����Ǘ��Ƃ��������A���ȋƖ������̏�͂܂��������Ă��Ȃ��Ƃ��낪�����B
�@�Ⴆ�A�A�}�]���E�h�b�g�R���͑q�ɂ╨���ɋ��z�̓��������āA�h�b�g�R���n���烊�A���n�ɓ����Ă��Ă���B98�N������99�N���ɂ����ăA�}�]���E�h�b�g�R���̏]�ƈ����͂S�{�߂��܂ő����Ă���B�f�C���[�O���������͂h�s�Y�Ƃ��ٗp���z�����Ă���ƌ��������A�A�}�]���E�h�b�g�R���Ƃ����h�s��Ƃ��Q�{���R�{���z�����Ă���̂́A��IT����ւ̑Ή��ł���B
�@�Ɠ����ɁA���ۂɂ��X���\���ď��������Ă�����Ђ��A�}���ɃC���^�[�l�b�g�Ή���i�߂Ă���B���A���n�u�����h���h�b�g�R���n�Ƃ��Ă̑Ή������������A���h�b�g�R���n�Ƌ�������p��99�N����e�Ǝ�Ŗ{�i�����Ă���B
�@���ɃX�[�p�[�Ȃǂ̏����Ƃł́A�C���^�[�l�b�g���̔��Ǝ҂̋}�i�ɑR���āA�C���^�[�l�b�g�̔��ƓX�ܔ̔��̗��̘H���I�݂Ɍ������p���ċ����͂�Ԃ��Ⴊ�ڗ����Ă���B�����Ԑ����A���Z�Ȃǂł��A�����̃u�����h��Ƃ��l�b�g��Ƃ̊�����悤�ɂȂ��Ă���B�h�b�g�R���n�̊����������ߒ����}�����̂́A���̓����Ɩ����ł͂Ȃ��B�V�����킹�Ẵl�b�g�ł̋����͂������炪�{�ԂƂȂ�B
�@���{�̓T�C�o�[�n�ƃ��A���n�������ɐi�ށB�V���h�b�g�R���̓o��ƁA�����̃u�����h��Ƃ̃h�b�g�R�����Ƃ���ĂɃ��[�C�h����Ԃɂ���B���������āA�V���h�b�g�R���ɂƂ��Ă̊��̓A�����J�ȏ�Ɍ��������̂�����B
�@�Ȃ��A�t������A���{�͌g�ѓd�b�̐Z���x�A�g�����ݓx�����̐�i�����瓪������o���Ă���A�l�b�g�r�W�l�X�̎p������Ȕ��B�̕��������ǂ�\��������B�f�W�^���e���r���X�^�[�g���x�ꂽ�Ƃ͂����A�n��g�e���r�̐Z���x�̐[���A�e���r�ǂ����f�B�A�s��ɐ�߂�ʒu�̓��ꐫ�Ȃǂ���݂āA�����I�ɂ͑����ɔ�׃e���r�n�ɂ��l�b�g�r�W�l�X�����x�ɔ��B���邱�Ƃ��z�������B�č��^��i�r�W�l�X��@�̒��A���͕K�����������Ƃ͂Ȃ�܂��B
8.3�@�d�q���������
8.3.1�@�A�����J���ƂƂ̊ւ��
�@���ʐM����͋K���ɘa���i�݁A���{���h�s�ɉʂ��������͏������Ȃ��Ă����Ƃ����̂���ʘ_�ł��������A�d�q��������{�i������ɏ]���A�t�ɐ��{�Ƃ̊ւ�肪�N���[�Y�A�b�v�����悤�ɂȂ��Ă����B
�@�C���t�������ɑ���o�ϋK���͓P�p�̕����ɂ���B�������A�d�q������́A�C���t���̏�ŗ����R���e���c��A�v���P�[�V�����̕��삾�B������A�Í���F�A�Z�L�����e�B��v���C�o�V�[�ی�̂悤�ɁA���Z�⍑�h���܂ލ��Ƌ@���ɗ��ސ��x�ɐG��邽�߁A���Ɛ���Ƃ̂�����肪�����Ȃ�B����܂Ŋe�����{�̃R���e���c����Ƃ��ẮA�e���r��f����ǂ��������Ƃ����S�����S���������A������鐭�{�֗^���������Ȃ��B
�@�Ƃ͂�����r�I�A�����J�͐��{�֗^�����Ȃ�����Ƃ����p������{�ɂ���B�����������̗��v�i����Ƃ����v�z���蒅���Ă��邩�炾���A����ɉ����A������Ƃ̋����͂��������߁A���̋����͂𐢊E�s��ɔ�������ɂ́A�A�����J�ȊO�̍��̐��{�֗^���ア�قǍD�s���Ƃ������_������B
�@�A�����J�̖ڕW�́A���E�I�ȗD�ʐ����ǂ��m�����A�O�����ɔ��������Ă��������B���Ƃ��Ίł͓P�p���悤�ƌ����B�A�����J�͔���肾���炾�B����A���쌠�͕ی삷��悤�����ɓ���������B�A�����J�̓R���e���c�������Ă��邩��A�R���e���c�̐��Y���l�̌���Ƃ��Ē��쌠����������͓̂��R�̂��Ƃ��B�[�j���������ɂ悱���A�������Ŏ��ȁA�ƌ����Ă��邾���̂��ƁB�A�����J�̐헪�͏�ɒP���ɓǂ݂Ƃ��_���������B
�@�e���̐헪�����炩�ɂȂ��Ă������߁A���ے�����98�N�ȍ~�A�}���`�̏�ł̊t�����Ղ��{�i�����A99�N�ɂ͎l�ɒʏ���c�Ȃǂ̏�ŁA�A�����J�ƃ��[���b�p�̗��ꂪ�Η������ʂ��}���Ă���B2000�N�V���̉���T�~�b�g�ł�IT����v�ۑ�ƂȂ�A�e���̊S���̒��S���߂�悤�ɂȂ����B
8.3.2�@�v���C�o�V�[�E�Z�L�����e�B�[
�@�v���C�o�V�[�ی�Ɋւ��ẮA���[���b�p�͍��Ƃ��K������X�^���X�������B�h�C�c�A�C�^���A�A�C�M���X�͏���ҕی�Ɋւ���@�����ɐϋɓI�ŁA�d�t�ł̎�g���������B����ɑ��A�A�����J�͖��Ԃ̎���Ή����d������X�^���X�ł���A�@���̑Ή��͘A�M���{�����B���{�����S�ƂȂ��Ă����B
�@���̂��߁A������Ȃ����ɑ��l���̑��t���ւ���Ƃ���EU�v���C�o�V�[�ی�w�j���߂���A�A�����J�ƃ��[���b�p�Ƃ̑Η��������Ă���B2000�N�U���ɂ̓A�����J�����݊��A�A�����J��Ƃ��K�����ׂ��w�j����邱�ƂƂȂ������A�������{�p���̈Ⴂ���璲����K�v�Ƃ��鎖�Ԃ������邱�Ƃ��z�肳���B
�@�������A�����J���d�q��������{�i������ɂ�A���ԑΉ��̌��E�ɂ����ʂ���悤�ɂȂ��Ă���B�q������l������肷��ɓ������Đe�̓��ӂ�K�v�Ƃ���@����2000�N�S���Ɏ{�s������ȂǁA�����ی�ɂ͗͂����Ă������A����ɂU���A�e�s�b���l���ی�̖@�K�����K�v�ł���ƕ\������Ɏ���A��{�I�ȕ��j�]���ɒʂ��铮���Ƃ��Ē��ڂ����B
�@�Z�L�����e�B�[�̒��S���߂�Í��̈����̓A�����J�̓i�[�o�X���B�Í��̋Z�p�⏤�i�����O���o���邱�ƂɊւ���K���͊ɘa����Ă��Ă��邪�A���̐����Ƃ��ĂƂ炦�ăR���g���[�����Ă���A��������̉ۑ�͍��ې헪�̏�ŏd�v�Ȉʒu���߂Ă������ƂƂȂ낤�B
�@�d�q������F�̐��x�ɂ��Ă��@�I�Ȏ�g���Ȃ���A���{�ł̖@�����Ƃقړ�������2000�N�U���ɂ͖@�����������Ă���B�N�����g�������͂Q���ɂ̓Z�L�����e�B�����̂��߂̗\�Z�g�[��\�����Ă���B�C���^�[�l�b�g���p���ȍ~�A���ԑΉ����e�[�[�Ƃ��Ă����A�����J�ɂ����āA99�N����2000�N�ɂ����āA�A�M�c��E���{����A�̊֗^����̂��Ă��Ă���_�ɒ��ӂ�v����B
8.3.3�@�d�q���{
�@�d�q���{�̐���̈Ӗ��Ƃ��āA�����̗��������シ��Ƃ������Ƃ͂�������A���{���C���^�[�l�b�g�̗��p��̂ɂȂ�A���A�R���e���c�̃v���o�C�_�ɂȂ�Ƃ������Ƃɂ��A���S�̂̂h�s���𑣐i������Ƃ����Ӗ������ɑ傫���B
�A�����J�̓S�A���哝�̂����S�ɂȂ��ď����J������Ƃ��A�C���^�[�l�b�g�Ŏ��ޒ��B������Ƃ������ƂɐϋɓI�Ɏ��g��ł���B2007�N�ɂ͐Ŗ��\���̓d�q����80���܂ŒB������ڕW���f���Ă���B
�@�Ȃ��A���̕���ł́A�A�����J�ȏ�ɃC�M���X�̃u���A�����������Ȏp���������Ă���B�S�s���葱�̓d�q����2008�N�܂łɒB�����邱�ƂƂ��Ă���A2000�N����͓d�q�葱�𗘗p���Ĕ[�ł����鏬��Ƃɂ͐ŋ������������Ă��Ƃ����a�V�Ȏ{����������Ă���B
�@���{�������O�̃~���j�A���E�v���W�F�N�g�ŁA2003�N�x�܂łɍs���葱�̐\���⍑�ł̐\�����C���^�[�l�b�g�ɏ悹�邱�ƂƂ��Ă���B�d�q���{�ւ̎�g�͊e���ɂ����ďd�v�Ȑ���ɂȂ��Ă����Ǝv����B
8.3.4�@�R���e���c�K��
�@�R���e���c�K���͏]���A�e���r��W�I�̔ԑg�̋K�������S�ۑ�ł������B�����Ǒ��A���U�Ό��Ȃǂւ̑Ή������Ƃ̊S�����B��i���ł̋K���h�̓t�����X�ŁA�K�����ǁi�Ɨ������s���@�ցj�ɂ�錵�i�Ȓ��ڋK����~���Ă���B���{�͐R�c�@�ւ�������Ǝ҂��u���ׂ��Ƃ����ԐڋK���ŁA���e�ʂ͎����I�ɖ��K���Ƃ������قȐ��x�ƂȂ��Ă���B�A�����J�͂e�b�b�����ڂɋK�����錠����L���Ă��邪�A�t�����X�قǂ̋����͂Ȃ��A����Γ����̒��ԂɈʒu����B
�@�����Ŗ��ɂȂ�̂��C���^�[�l�b�g�̃R���e���c���ǂ��Ƃ炦�邩�����A�e���Ƃ��C���^�[�l�b�g�̕��y�ɔ����A���X�ɐ��{�֗^�̋����̕����Ɍ������Ă���悤���B�܂��A���̓x�����͕����K���̋���f�������̂ƂȂ��Ă���悤�Ɍ���B
�@�����A�A�����J�́A96�N�d�C�ʐM�@�ŒʐM�̓��e�K������������A98�N10���ɂ͎����I�����C���ی�@�������肵�����A���ꂪ�ٔ���̑����ɂȂ�A���ǁA���x���̂��̂��蒅���Ă��Ȃ��B���@�E�s���E�i�@�̃v���C���[������g��Ő��x���m�肵�Ȃ��Ƃ�����Ԃ̓A�����J���x�̓����ł�����B
�@�Ȃ��A���{���������e�̋K�����ɂ��܂܂ɕۂĂ�̂́A�����▯�Ԋ�Ƃ̎����p�ŎЉ�K�͂�ۂ����邱�Ƃ��������̂ł���A���̕����K���t��� |